私たちが普段目にする情報は必ずしも正しい情報ばかりとは限りません。マイナンバーカードほど認知度が高く、間違った情報が広がっているものは日本で他にないでしょう。そこで今回は、マイナンバーカード、マイナンバー制度に関するウソ・ホントをクイズ形式で解説していきます。
こんな人におすすめ
- マイナンバーの知識を深めたい方
- マイナンバーについて気になる情報の真偽を確かめたい方
この記事でわかること
- マイナンバーについてよくある噂の真偽を知ることができる
- マイナンバーと個人情報の関係について知ることができる
マイナンバーカードに関するウソ・ホント
Q.「マイナンバー」=「マイナンバーカード」?
A.【ウソ】マイナンバーとマイナンバーカードは全くの別物
マイナンバーは12桁の個人番号そのもので全住民に付番されています。マイナンバーカードは申請に基づき交付される物理カードです。
マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)使用時の本人確認を1枚で行えるようにした顔写真付きのカードであり、対面でもオンラインでも本人確認手段として幅広く利用することができます。
【マイナンバーとマイナンバーカードの違い】
| マイナンバー | マイナンバーカード | |
|---|---|---|
| 取得方法 | 意志に関わらず付与される | 本人の申請で交付 |
| 利用方法 | 税・社会保障・災害対策の3分野 | 本人確認で幅広く利用 |
| 情報の確認方法 | 情報を一元化しない | 電子証明書によりオンラインで本人確認可能 |
| 使用用途 | 本人確認のために番号・身元の確認の義務付け | 電子証明書やICチップの空き容量は民間活用も可 |
マイナンバーカードは「番号確認」のための本人確認にも、マイナンバーの確認が必要ない「本人確認」のためにも利用可能です。

Q.マイナンバーカードは身分証明書として利用できる?
A.【ホント】マイナンバーカードは様々なシーンで身分証明書として利用できる。
マイナンバーカードは、法令に基づき居住地の市区町村の対面窓口で厳格な本人確認を行った上で発行される、最高位の公的な身分証として位置づけられています。
マイナンバーカードの券面には顔写真、⽒名、住所、⽣年⽉⽇など情報が記載されているため、写真付きの本人確認書類として、さまざまなシーンで活用が可能です。
ただし、裏面に記載されているマイナンバーは、法令で定められた税・社会保障・災害対策以外の手続きで事業者が利用することは禁止されています。マイナンバーカードのコピー提出時には注意しましょう。
【豆知識】
なお、身分証明書として運転免許証を提示した場合、マイナンバーカードよりも多くの情報を他者に見せることになります。例えば、運転免許証の発行番号には初回発行年が含まれており、免許証の有効期限の年数とあわせてみることで、違反運転者かどうかを推測することができてしまうのです。マイナンバーカードであれば、このような余計な情報を他人に知られる心配はありません。
Q.マイナンバーカードから芋づる式に個人情報が漏れる?
A.【ウソ】マイナンバーカードでわかる情報は限定的かつ分散管理されている
マイナンバーカードの券面(表側)には、以下の情報が記載されています。
- 基本4情報(住所・氏名・生年月日・性別)
- 顔写真
- マイナンバーカードの有効期限
- 電子証明書の有効期限
- 追記欄の情報(住所や氏名の変更情報など)
- 臓器提供意思の有無
ICチップ内を含めてカード自体に本人の税や年金、病歴などの個人情報は含まれておらず、カードを紛失してもこれらの情報が流出することはありません。
また、マイナンバー制度では、個人情報が共通データベースで一元管理されることはなく、各機関で必要な情報を必要なときだけやり取りする「分散管理」の方法が取られています。
そのため、そもそもマイナンバーカードには税情報や病歴などは含まれておらず、情報が芋づる式に漏洩してしまう恐れもありません。

【豆知識】
マイナンバーカード裏面の追記欄には、旧姓などを追記するため、カード提出時に旧姓を知られてしまう可能性はあります。

Q.マイナンバーカードは盗まれると他人に悪用される?
A.【ウソ】マイナンバーカードは悪用されるリスクは低い
マイナンバーを利用する手続では、顔写真付きの本人確認書類の提出が義務付けられており、金融機関への書類提出時なども本人確認が必要です。
マイナンバーカードにも顔写真がついており、金融機関の窓口などではカードの写真と本人の顔を照合するため、他人が本人になりすまして手続することは困難です。
また、マイナンバーカードの盗難に遭ったり、紛失した場合は、コールセンターに電話することでカードの一時停止措置が取られ、第三者によるなりすまし利用を防止できます。
マイナンバーカードの電子証明書にアクセスするためには、発行時に自分で決めた暗証番号(パスワード)が設定されているため、紛失したり盗難にあった場合でもオンラインでなりすましを行うことはできません。さらに、この暗証番号は3〜5回連続で間違えると電子証明書はロックされ、以後利用できなくなります。
パスワードを忘れてしまった、あるいはロックされてしまった場合は、住民票がある市区町村の窓口で再設定の手続きが必要です。
マイナンバー制度に関するウソ・ホント
Q.マイナンバー制度で会社に副業がバレる?
A.【ウソ】副業がバレる原因はマイナンバー制度とは関係がない
マイナンバー制度が開始されたことにより、会社が税務署に提出する書類である源泉徴収票や確定申告書にマイナンバーを記入することになりました。これにより、「マイナンバー制度によって会社に副業がバレるのではないか」と心配する人もいます。
副業が会社にバレる一番の原因は、住民税税額によるものです。サラリーマンの場合、住民税は給与支払者を経由して納税義務者に通知されることになっており、副業により住民税が上がったことで会社に不審に思われるケースが大半です。つまり、副業がバレる原因はマイナンバー制度とは関係がないのです。
また、税務署などの行政機関から会社に対し、特定の従業員が副業している事実を知らせることはなく、行政は会社からの問い合わせに応じることもありません。
会社に副業がバレたくない場合は、これまでどおり確定申告書における住民税の納付方法で「自分で納付」を選択しましょう。これにより、副業分の住民税は会社に通知されることなく、自宅に届いた納付書で納付を行うことができます。
Q.マイナンバーを利用する手続きにおいて国や自治体が口座番号や口座の暗証番号を電話で聞くことはない?
A.【ホント】国や自治体がマイナンバー手続きで口座番号や口座の暗証番号、クレジットカード情報などを聞くことはない。
マイナンバーは法律によって利用範囲が決められており、社会保障、税、災害対策の3つの行政分野に限り利用が認めらています。マイナンバーの利用手続では、原則として顔写真付きの身分証明書などによって本人確認をすることが義務付けられています。
そのため、電話などで国や自治体が口座番号や口座の暗証番号、資産の情報、家族構成などの個人情報を聞いたり、金銭を要求することはありません。もし国や自治体の職員を名乗って「マイナンバー手続きで個人情報を教えてほしい」と言われても、絶対に教えないようにしてください。
【参考】
マイナンバーの利用のうち「税分野」においては、銀行が預金口座とマイナンバーを紐づけて管理することが求められており、投信・債券などの取引にはマイナンバーの提出が必須になっています。
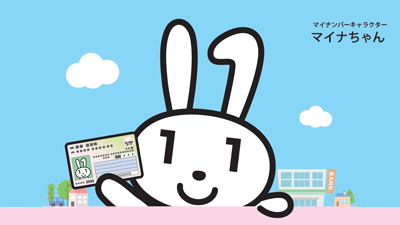
Q.マイナンバー制度で行政職員に所得などの情報が見られてしまう?
A.【ウソ】マイナンバー制度では行政職員は個人の所得情報などを閲覧できない。
関係法令の改正により、2018年1月から、預貯金者の情報をマイナンバーにより検索することができる状態で管理しなければならないことになりました。しかし、これは金融機関の破たんや災害時に円滑な預貯金の払い戻しをしたり、税務調査や生活保護などの資産調査をするために活用される制度です。
つまり、マイナンバー制度によって行政職員があらゆる住民の所得情報を得られるようになったわけではないということです。税務調査や生活保護調査など、特定の状況で行政職員が職権により資産調査を行うことができる点は従来通りであり、これらの調査にマイナンバー制度が活用されると理解しましょう。
マイナンバーは正しい知識を身に着け、正しく恐れることが大切
マイナンバーカードやマイナンバー制度については、ネットなどを中心に誤った情報が拡散されることがあります。このような情報に騙されないためにも、マイナンバー制度に関する正しい基礎知識を身に付けることが大切です。
みんなのデジタル社会ではマイナンバー制度やマイナンバーカードに関するナレッジを多数発信しています。ぜひ正しい知識を身に着け、生活のために役立ててください。



